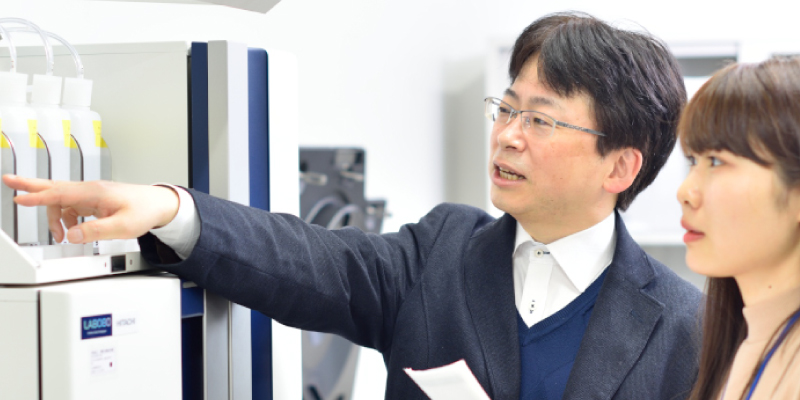博士課程前期課程 統合バイオ科学技術領域
さまざまな生命現象を統合的に理解するために、生物個体や細胞の機能について分子生物学、生化学、細胞生物学、生理学あるいは生態学などの観点から教育・研究を行います。
生命現象を統合的に理解するために、生命機能を司る生体分子をバイオサイエンスの技術を用いて改変し、新しい機能を持つ生体分子を創出する技術や、高度に分化した細胞の機能を細胞工学と微細構造解析を用いて解析する技術、また情報伝達や免疫機構を動植物の個体レベルで研究する技術、環境における生物の多様な生態系をさまざまな研究手法で解析する技術と共に、外国語によるコミュニケーション技術や生命倫理・科学者倫理に関しての教育を行います。
この様な教育・研究を通して、さまざまな生命活動を統合的に理解し、生命活動の機構解明に貢献する人材や人類に役立つバイオ技術を開発する人材を育成します。
学内進学の動機

小川 愛楽 さん
博士課程前期課程
統合バイオ科学技術領域 1年
(滋賀・県立東大津高等学校出身)
「この研究に打ち込みたい!」と思えるテーマに出会えたことが進学の理由です。転機となったのは3年次の研究室紹介。当時、本学に赴任されたばかりの齋藤茂先生が、「環境の変化に応じて生きものが姿かたちを変える『環境適応』に、感覚神経の温度センサーが関わっている」というお話をされました。
そのときは研究内容の半分も理解できなかったのですが、難解なテーマだからこそ自分なりに挑みたいという気持ちになりました。大学院への進学は学費がひとつの気がかりでしたが、大学院生が授業の補助を行うTA制度を利用して学費の足しにしています。学内で研究を続けながら、自分自身の学び直しの機会になる。とてもいい制度だと思います。
現在は、温泉地に生息するリュウキュウカジカガエルの温度センサーについて調べています。なぜこのカエルが高温耐性を持つようになったのか。進化の過程をたどりながら、その要因を特定しようとしています。
そのときは研究内容の半分も理解できなかったのですが、難解なテーマだからこそ自分なりに挑みたいという気持ちになりました。大学院への進学は学費がひとつの気がかりでしたが、大学院生が授業の補助を行うTA制度を利用して学費の足しにしています。学内で研究を続けながら、自分自身の学び直しの機会になる。とてもいい制度だと思います。
現在は、温泉地に生息するリュウキュウカジカガエルの温度センサーについて調べています。なぜこのカエルが高温耐性を持つようになったのか。進化の過程をたどりながら、その要因を特定しようとしています。