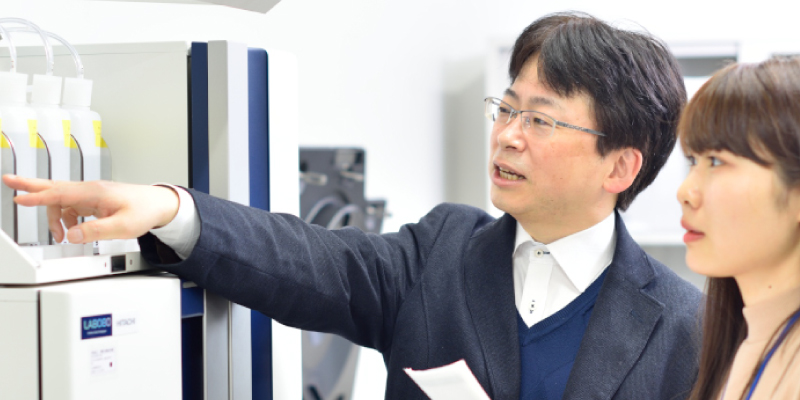放射線生物学
専門教育科目の科目紹介(2014年度開設予定)
| 主に1年次で履修 |
主に2年次で履修 |
主に3・4年次で履修 |
||
|---|---|---|---|---|
| 3学科共通 専門コア科目 |
|
|
4年次卒業研究 |
|
| 学科 | バイオ サイエンス |
|
|
|
| アニマル バイオ サイエンス |
|
|
|
|
| コンピュータ バイオ サイエンス |
|
|
|
|
講義室を覗いてみよう!
【2013年度例】
2014年度からの教育プログラム実施により、科目の名称、内容、設置について変更する場合があります。
生命倫理
今問われている倫理テーマをグループ討論で多角的に考察

iPS細胞の登場など、めざましく進展するバイオは、生命の領域と密接なものになっています。そのため、バイオの研究・技術者にとっては、生命倫理はとても重要な意味を持っています。本学では、2年次の必修科目になっています。
講義では、神経内科医や神主でもある産婦人科医、法学者などを学外から講師として招き、「もし、あなたが胃がんで余命3ヵ月なら?」などの問題提起をいただき、10数人の小グループに分かれて討論し発表しました。他にも環境や法などの広い視点から生命倫理を考えます。
生命倫理を自らの問題として捉え、自分とは異なる意見がありなぜ異なるのかを理解し、自分の意見を述べる力を養います。(担当:三輪正直先生)
生化学I(生体成分化学)
生体を構成している物質の視点から、生命のランドスケープを描く

生命を原子・分子レベルで化学的に理解・解明するのが生化学です。全15回の講義を通して、生体を構成している主な物質であるアミノ酸やペプチド、タンパク質、糖質、脂質、核酸、酵素、ビタミンなどを細胞と関連付けて網羅し、構造と機能、生体反応や調節機構を理解して、最終的に生体構成物質の視点から生命のランドスケープ(概観)を描けるようにするのが目標です。
これは生理学や遺伝学、細胞学など、これから学ぶすべての科目の基礎となり、生命、個体、環境、ひいては地球を理解することにつながるので、バイオサイエンスを志す上で、最も基盤となる科目だと言えます。(担当:向井秀仁先生)
医学生物学
滋賀医科大学との連携授業で、免疫学の基礎を学ぶ

最近の医学・医療に関する進歩は目覚しいものがあります。本学では、大学間連携により滋賀医科大学の教員により、医学生物学、人体解剖学、アルツハイマー病などに関する連携授業を行っています。
医学生物学では、小笠原一誠教授、伊藤靖准教授、石垣宏仁特任助手、仲山美沙子助教により3年次生を対象に15回の講義を行っています。病原体を排除する免疫系について細胞レベルおよび分子レベルで学び免疫学の基礎を身につけます。また、この異常としてのアレルギーや自己免疫疾患について学び、疑問を持つことを学習することの到達目標にしています。この授業の一部は、滋賀医科大学との遠隔授業で行っています。(担当:小笠原一誠先生、伊藤靖先生、石垣宏仁先生、仲山美沙子先生)
動物生理学
ヒトを中心に生理的機能の知識を網羅、資格につながる知識を修得

生命科学は、生化学・生理学・組織学の3本柱で成り立っています。組織学は解剖学的知見から、生化学は反応論的知見から考えるのに対して、生理学はそこに時系列や変化などの動きが加わった視点から考える学問です。
この講義では、看護師等の医療専門技師が使うものと同じ教科書を用いて、神経・感覚、骨格・筋肉、循環・血液、消化・吸収、生殖などの生理的機能を、ヒトを中心に解説し、医学が要求する基本的な知識を網羅します。
また、ヒトと比較しながらマウスやラットなど動物の知識も深め、最終的に、適切な専門用語を用いて説明できる知識、食品衛生管理者や実験動物技術者の資格につながる知識の修得をめざします。(担当:永井信夫先生)