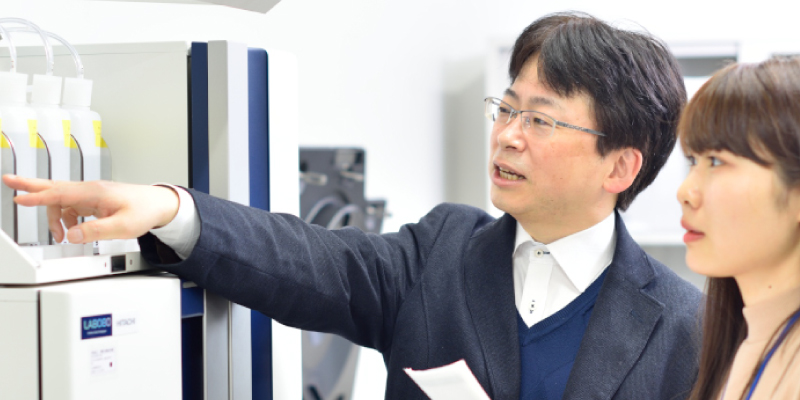バイオサイエンス学科の学び
カリキュラムポリシー
本学科では、生物学、農学、薬学、医学などの幅広い領域にわたるバイオサイエンスを、分子から個体、さらに環境レベルに至る階層的生命観を縦糸に、基礎から最先端までの科学的知見を横糸に織り上げながら総合的に学びます。
基本から実践に至るバイオサイエンスの知識と技術を修得し、食料、医薬、エネルギー、環境などの分野の社会的ニーズに対応できる次世代を担う人材の育成を、教学の目標に据えています。そのため、「創薬・機能物質プログラム」、「環境・植物制御プログラム」、「遺伝子・細胞新機能プログラム」の3つの専門教育プログラムを設置しています。
Ⅰ 本学科では、1年次から学部共通一般教育プログラムと学部共通専門コアプログラムを順次履修し、2年次からは、バイオサイエンス学科の3つの専門教育プログラムから1つを選択して学びます。
- 講義科目では、生命現象の基礎的な理解から関連産業の現状に至る応用的な分野まで、広範な知識を獲得します。
- 実験・実習は、生物と化学の基礎実験からスタートし、遺伝子、分子、細胞、環境のそれぞれの基礎と応用、さらに創薬・機能系、環境・植物系、遺伝子・細胞系の専門実験へと発展させ、4年一貫の体系的実験・実習により、段階を追った実験技術の積み上げを図ります。日進月歩のバイオサイエンス分野において、将来の新技術を吸収できるだけの技能基盤を築きます。
- 3年次から配属される研究室では、専門領域を深めた研究を通し、より実践的な技術と論理的思考力を身につけます。
Ⅱ 「創薬・機能物質プログラム」では、創薬、機能物質の開発と生産、環境評価などの発展的バイオ分野において、「環境・植物制御プログラム」では、生態系維持、環境修復、生物応答、植物成長制御などの環境制御分野において、「遺伝子・細胞新機能プログラム」では、予防医学、個別医療、細胞技術に基づく再生医療などの先端生命科学分野において、それぞれ活躍できる人材の育成を目指しています。
Ⅲ バイオサイエンス分野の研究や知識・技術の修得と活用に不可欠な、コンピュータ実習を必修科目として配置します。
Ⅳ 国際化社会に対応できる英語力を養うため、基礎段階から発展段階までの英語科目を履修します。
Ⅴ 1年次から自己啓発に重点を置いた演習を行い、自発性・自主性を育てます。