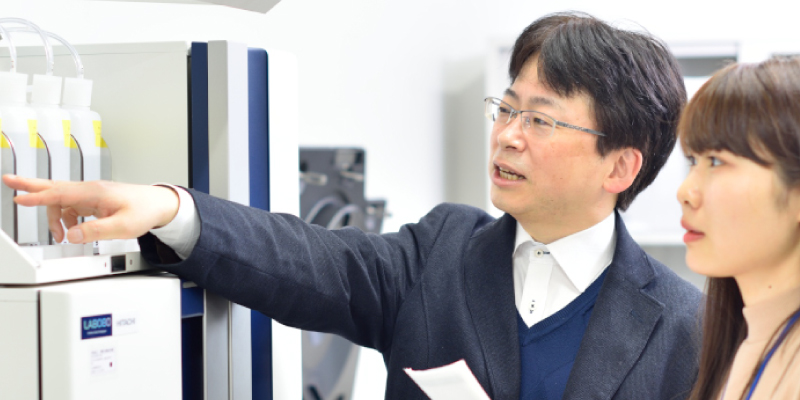先輩の研究室を拝見!

細胞組織構造学研究室・山本章嗣先生
稲垣貴俊さん(滋賀・ 県立伊香高校出身)
電子顕微鏡で目に見えない細胞の世界について研究
電子顕微鏡を使って、細胞質の一部が膜に包まれて分解されるオートファジーという現象や、ゴルジ体、ミトコンドリアなどの細胞小器官の働きなど、目に見えないような小さな細胞の世界について研究しています。先生は電子顕微鏡のエキスパートなので、親切丁寧に使い方などを教えてくれます。
先生は研究のことだけではなく、学生生活での悩みや就職活動の相談などにも、親身になって相談に乗ってくれます。みんなとても仲が良いので、和気あいあいとした雰囲気ですが、研究に対する責任感はみんなが持っているので、お互い刺激し合いながら研究をしています。
私たちの研究室は、電子顕微鏡を使って目に見えないような小さな世界を見てみたい、和気あいあいとした雰囲気が好き、エキスパートのもとで何か一つ極めてみたいという学生に、ぴったりの研究室です。

時空動物学研究室・野村慎太郎先生
小八木拓郎さん(大阪・私立上宮太子高校出身)
社会に貢献するという使命感を持って
私は現在、傷ついた組織が元に戻ろうとする組織修復反応について、興味を持っています。この反応が、途中で停止や遅延、過剰な修復反応をする事が病気の原因となる事を学びました。卒業研究では皮膚、筋肉の修復反応に関係する遺伝子の発現変化を調べる予定です。
研究室の野村先生には、「君はそろそろ社会に貢献する時期が来ている。使命感を持って学生生活を過ごしてほしい」と言われました。これからは今よりも高度で正確な技術を修得したい、勉強もテストのためでなく一生使える知識を身につけたい、と考えるようになりました。毎日の努力を積み重ね、技術職につけるよう努力したいと考えています。
私自身は長浜に下宿していて、料理と風景写真を趣味にしていますが、こちらの方ももっと高いレベルに挑戦し、自分の世界を広げていきたいと思います。

動物分子生物学研究室・齊藤 修先生
安田隆ノ介さん(大阪・私立清風高校出身)
ナメクジウオのTRPA1の機能を解析
種々の細胞内外の刺激により活性化される、細胞のセンサータンパク質ファミリーTRPチャネルの一つであるTRPA1は、動物の食性や生存戦略に合わせて機能変化していると考えられています。
私は、まだ誰も調べていない頭索動物であるナメクジウオのTRPA1をクローニングして、どのようなセンサーとして働いているかを研究しています。ナメクジウオは温かい浅海の砂の中に生息していて、脊椎動物の最も原始的な祖先に近い動物であると考えられています。このTRPA1の機能を解析することで、どのように進化してきたのかを考察します。
私たちの研究室では、年に一度、夏にキャンプに行っており、命洸祭で出店も行っています。また、サンショウウオ、カエル、メダカ、イモリ、エビやカメなど、沢山の生物が飼育されています。先輩方は親身でとても賑やかな中、楽しく研究しています。

動物生理学研究室・永井信夫先生
西谷あいさん(京都・府立鳥羽高校出身)
血液凝固におけるタンパク質などの細胞因子の影響を研究
私たちの研究室では、主に脳梗塞・線溶を扱っています。その中で私は血液凝固におけるタンパク質などの細胞因子が、どの様に影響するのかを研究しています。例えば、ケガをした際、損傷した血管表面にフィブリンという繊維がどんどんへばり付き、血管内にフィブリンの塊ができ、止血の役目を果たします。フィブリンが適切な大きさに調整され、血流を遮断せずに治癒を行うと考えられています。この血栓の調節には、アルツハイマー病の原因であるβ-アミロイドが関わっているという報告があります。そのβ-アミロイドが人にとってどのように作用するのかを調べていきます。
また、私たちの研究室ではマウスを扱い、病態からの回復メカニズなどの解明も行っています。
疾患について興味ある人、動物実験をやってみたい人はぜひ来てください。
食品分子機能学研究室・河内浩行先生
王 孟禹さん(中国山東省・淄博怡中外国语学校出身)
肉牛の血清を用いた肉質評価
私は、牛の霜降り肉に関する研究を行っています。霜降りとは牛肉の中に入る脂の事で、その脂は肉の血管に沿って入ることから、血液中の成分が脂肪を増やすように働きかけているのではないかと考えています。そこで、血液成分を調べて、牛が生きた状態で霜降りのレベルが予測できるようになれば、効率良く肉質を向上させることが可能となるのではないかと期待しています。
研究室はゴミ箱までカラフルで、明るい雰囲気に包まれています。実験もやる気が出ます。先輩たちはとても親切で、実験手法を丁寧に教えてくれます。先生は、実験の時はすごくまじめですが、普段はよく冗談を言われるので、研究室には笑いが絶えません。
この研究室は、食品の安全やペットに関する研究も行っています。食品の安全に関心がある人、ペットが大好きな人を大歓迎します!

比較動物学研究室・和田修一先生
和田翔太さん(京都・府立菟道高校出身)
扁形動物プラナリアの低酸素ストレス応答の解析
私の研究室は、学部生10人と院生1人で、男だらけのむさくるしい研究室ですが、みんな仲が良く、日々楽しく研究しています。
私は「扁形動物プラナリアの低酸素ストレス応答の解析」というテーマで研究しています。湖や海では、水質の悪化などにより、水中の酸素濃度が通常より低くなることがあります。私の研究は、動物がどのような遺伝子を使ってこうした低酸素化に対処しているかを調べることです。
研究室にはグローブやバットがあり、研究と遊びのメリハリがきいた研究室となっています。先生は学生の悩みを聞いてくださる、私たちの良き理解者です。
私が大学を目指す皆さんに伝えたいことは、大学生活は何をするにも自由な反面、何をするか自分で決めなければならないので、大学で自分が何を学び、どんな生活をしたいかを良く考えて欲しいということです。

エピジェネティック制御学研究室・中村肇伸先生
古川稚沙子さん(岐阜・県立長良高校出身)
受精卵から個体になるまでの謎を解き明かすエピジェネティクス研究
私たちの体はたった一個の受精卵から、少なく見積もって約200種類、60兆個もの細胞によりできています。父と母から受け継いだ遺伝情報は、一部の例外を除いて生涯変化することはありませんが、遺伝子の発現はそれぞれの細胞で異なっています。この違いは、「エピジェネティック制御」が生み出しています。
研究室では、精子と卵子が受精後にどのようにして体を構成する全ての細胞に変化できる状態に戻るのかについて、ノックアウトマウスを使って研究しています。世界中でこの研究室にしかいないマウスの解析は、とてもやりがいがあり、どのような結果が出るのか楽しみです。
先生は就職活動などの相談のとき、私たちの意見を尊重し、適切なアドバイスでサポートしてくださいます。また、普段は些細な話を楽しくできる親しみのある先生で、この研究室に入ってよかったです。