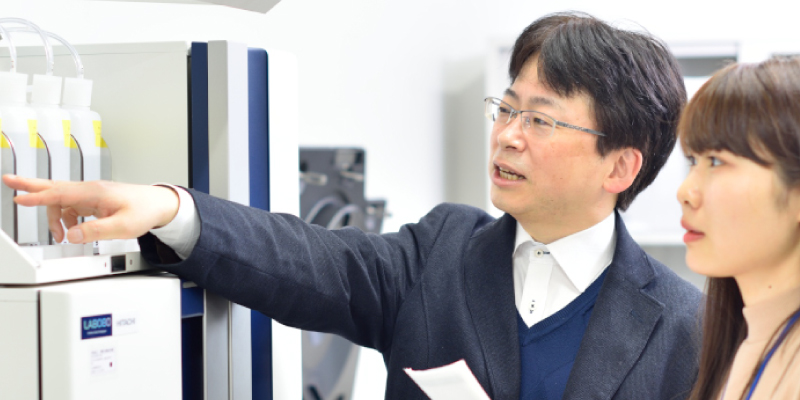環境生命科学コースの概要
 地球上には多様な生物が生存し、環境と調和した豊かな生態系を構築しています。環境生命科学コースでは、生物が生態系の中でどのように環境を認識し、互いに調和しているのかを分子の言葉で理解することを目的として研究を行っています。
地球上には多様な生物が生存し、環境と調和した豊かな生態系を構築しています。環境生命科学コースでは、生物が生態系の中でどのように環境を認識し、互いに調和しているのかを分子の言葉で理解することを目的として研究を行っています。
例えば、光など外界の刺激に対する動物の認識とその応答機構についての研究や、河川や湖沼に流れ込む内分泌攪乱物質が魚類等の生物に及ぼす影響とその機構に関する研究などを行っています。
また、植物の環境認識や病原菌に対する植物免疫の仕組みに関する研究や、微生物の生理機構と寿命の制御に関する研究、環境中に存在する生物が作り出す様々な生理活性物質に関する研究なども精力的に行っています。
私たちのこの様な研究は、豊かな生態系を永く維持するための基盤になると考えています。
期待される就職分野
生命科学関連の大学院・研究所・企業など、環境汚染や自然環境生物を利用した汚染浄化のプロフェッショナルとして、環境汚染の防止や環境浄化に取り組む研究機関・企業等において活躍することが期待されます。
履修モデル
| 1年次〜 | 2年次〜 | 3年次〜 | 4年次〜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 教 育 |
人文・社会 | 哲学 法学(日本国憲法) 歴史学 日本文化論 心理学 情報社会 科学技術史 |
文学 経済学 日本の歴史と文化(留学生) |
現代の社会と政治 | |
| 健康 | 健康保健学 | ||||
| 外国語 | 英語I 英語II 日本語I(留学生) 日本語II(留学生) |
科学英語I 科学英語II 英会話I 英会話II |
英語III 英語IV |
||
| スキル | 文章表現 プレゼンテーション技法 |
||||
| 情報 | コンピュータ実習 (情報科学演習)I コンピュータ実習 (情報科学演習)II |
||||
| 自然科学 | 数学I(数学基礎) 数学II(解析学) 数学III(線形代数学) 基礎物理学I(力学) 基礎物理学II(電磁気学) 化学I(有機化学) 基礎生物学 基礎化学演習 自然科学基礎実験 |
基礎統計学 | |||
| キャリア | ライフデザイン 長浜バイオ大学 魅力発見発信プロジェクト |
キャリア開発I 長浜まちづくり 魅力発見発信プロジェクト 論理的思考力開発 |
キャリア開発II | ||
| エッセンシャル | プログレス | アドバンスト | |||
| 専 門 教 育 |
講義科目 | 化学II(物理化学) 化学III(無機・分析化学) 生化学I(生体成分化学) 細胞生物学I 基礎微生物学 |
生命倫理 生化学II(代謝生化学) 環境生態学 環境分析化学 生命情報科学概論 安全学 タンパク質科学 細胞生物学II 機器分析概論 酵素科学 遺伝子科学 環境影響評価論 環境化学 生体高分子解析学 |
細胞工学 植物分子遺伝学 植物分子環境生理学 環境微生物学 生体分子応答学 応用微生物学 発生生物学 ウイルス学 生理活性物質概論 |
文献調査・講読 環境保全学 |
| 実験・実習科目 | 遺伝子科学基礎実験 分子科学基礎実験 細胞科学基礎実験 環境科学基礎実験 |
生命情報科学応用実習I 生命情報科学応用実習II 遺伝子科学応用実験I 遺伝子科学応用実験II 分子科学応用実験I 分子科学応用実験II 細胞科学応用実験I 細胞科学応用実験II 環境科学応用実験I 環境科学応用実験II |
遺伝子科学専門実験I 分子科学専門実験I 細胞科学専門実験I 環境科学専門実験I 環境科学専門実験II |
||
| 総合専門 | 卒業研究 | ||||
先輩の研究室を拝見!
植物分子環境生理学研究室・蔡晃植先生
寺沢 勇治さん(三重・私立海星高校出身)
植物病原菌への免疫反応を分子レベルで解明
 植
植
物工場で高機能野菜を作る研究や、植物病原菌に対して、動物のように自由に動くことができない植物が自己を守るために起こす免疫反応に関する研究を行なっ
ています。私の研究は、TIFY11dという特定の遺伝子が通常のイネに比べて過剰に発現している状態で、植物病原菌に対して起こる免疫反応を分子レベル
で解明していくことを目的としています。
研究室内では、学部生、院生、研究員のみなさんが熱意を持って研究に打ち込んでおり、研究打ち合わせや報告会でも、研究に対して様々な議論が繰り広げられています。また、指導教員の蔡先生も、学生たちにとても情熱的に指導してくださり、毎回勉強になることばかりです。
そんな研究室で実験を行なっている中で忙しく感じることもありますが、毎日とても充実した学生生活を送れていると感じています。
環境応答遺伝学研究室・山本博章先生
澁谷 仁寿さん(岐阜・県立大垣東高校出身)
動物を使って色素細胞の機能を解析
 自
自
然界にはたくさんの色が溢れています。そのような色をつけることに関与しているのが、色素細胞です。もちろん、色素細胞は色をつけるためにも働いています
が、まだまだ未知の機能が隠されていると予想されます。実際に、色素細胞の異常が原因で、難聴になったり、眼の発生がうまくいかなかったりします。そこで
色素細胞はどのようにして生まれ、どのような機能を持っているのかを解析しています。
09研究室では、マウスやニワトリの卵など、動物を使った実験をしています。和気あいあいとしており、頼りになる先輩ばかりです。
そのなかで、互いに刺激し合いながら研究しています。先生は、いつも私たちのことを気にかけてくださる優しい方です。でも、時々、私たちを驚かせるような
ことを言って、私たちを楽しませくれます。
環境微生物学研究室・向由起夫先生
野口友里亜さん(大阪・府立春日丘高校出身)
寿命の長さに関わる酵母の化合物をNMR で解析
 酵
酵
母を用いた寿命制御機構と転写抑制機構の解明、また、アユ冷水病ワクチンの開発を行っています。私の研究テーマは、酵母の細胞内代謝物のNMR解析です。
酵母の細胞内代謝物が株ごとでどのように異なるのかNMRを用いて分析し、寿命の長さに関わっている化合物を同定することで、寿命がどのようにして調節さ
れているのかを明らかにしようとしています。
指導教員の向先生は、分からない事があれば一つひとつ丁寧に教えてくださり、研究や進路についても親身になって相談に乗ってくださ
います。研究室の先輩方は些細な質問にも丁寧に答えてくださいます。もちろん研究以外にも、お花見やラボ旅行など楽しいイベントがあります!私はこの研究
室で先生や先輩方から新たな事を学んで充実した日々を送っています。
環境分子応答学研究室・池内俊貴先生
佐村木 友紀さん(滋賀・県立守山高校出身)
環境ホルモンを測る遺伝子組み換え細胞の開発
 高校生の時に細胞の情報伝達に興味を持ち、この大学を選びました。研究室は、水環境と内分泌攪乱物質をテーマにしています。
高校生の時に細胞の情報伝達に興味を持ち、この大学を選びました。研究室は、水環境と内分泌攪乱物質をテーマにしています。
水中には様々な生物がいますが、水が農薬などの化学物質で汚染されることで、繁殖できないようになってしまいます。それは、外から
入ってくる化学物質が、体内のホルモンの代わりに細胞の受容体に結合して間違った情報を伝えてしまうからです。例えば、ドーパミンは人間では神経伝達物質
として知られていますが、魚では卵の発達を抑制する働きもしています。このドーパミンに似ている化学物質が川などに溶け込むと、魚は繁殖できなくなってし
まいます。そこで、ドーパミンが働くしくみを利用して、内分泌撹乱物質を測る遺伝子組み換え細胞を開発しています。
先生も先輩も丁寧に指導してくださるので、一所懸命実験に取り組むことが出来ます。